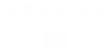Informaiton
プロが解説!失敗しないコンタクタ メーカー 比較:用途別おすすめと選定ポイント
コンタクタ選びで迷っていませんか?本記事では、三菱電機、富士電機、オムロンなど国内主要メーカーのコンタクタを徹底比較し、それぞれの強みや得意分野を解説します。モータ制御やヒータ制御、盤内省スペース化、特殊環境など、あなたの用途に合わせた最適なコンタクタの選定ポイントを網羅的にご紹介。失敗しないための定格確認や安全規格、メンテナンス性まで、プロ目線で解説します。この記事を読めば、あなたの設備にぴったりのコンタクタが見つかり、安心して選定できるようになります。
1. コンタクタ選びで失敗しないために
コンタクタは、産業機械や設備のモータ、ヒータ、照明などの負荷を安全かつ効率的に制御するために不可欠な電気部品です。その選定を誤ると、単なる部品交換のコストに留まらず、生産ラインの停止、設備全体の故障、さらには重大な事故につながる可能性もあります。
適切なコンタクタを選ぶことは、設備の安定稼働、電力効率の最適化、そして何よりも作業者の安全を確保する上で極めて重要なのです。
1.1 コンタクタ選定における主な落とし穴
「とりあえず安価なものを選ぶ」「以前と同じものを選ぶ」といった安易な選定は、後々の大きなトラブルの元となります。以下に、コンタクタ選定で陥りがちな失敗例とそのリスクを挙げます。
1.1.1 過剰スペックによる無駄なコスト増
必要以上に高い定格電流や多機能なコンタクタを選んでしまうと、初期導入コストが無駄に高くなるだけでなく、盤内スペースの圧迫や配線の複雑化を招くことがあります。
1.1.2 過小スペックによる早期故障と事故リスク
逆に、負荷容量に対して定格が不足しているコンタクタを選んだ場合、頻繁な故障や短寿命につながります。最悪の場合、過負荷による発熱や溶着が発生し、火災や感電事故のリスクを高めることになります。
1.1.3 環境条件への不適合
設置環境の温度、湿度、振動、粉塵などの条件を考慮せずに選定すると、コンタクタの性能が十分に発揮されず、予期せぬトラブルを引き起こす可能性があります。特に特殊な環境下では、耐環境性に優れた製品の選定が不可欠です。
1.1.4 メンテナンス性・互換性の軽視
将来的なメンテナンスや交換部品の入手しやすさを考慮しないと、故障時に部品調達に時間がかかり、設備停止期間が長期化する恐れがあります。また、既存システムとの互換性も重要な要素です。
1.2 この記事で得られること
本記事では、このようなコンタクタ選定の落とし穴を避け、お客様の用途に最適なコンタクタを確実に選べるよう、以下の点について詳しく解説します。
コンタクタの基本的な種類と役割
国内主要メーカー(三菱電機、富士電機、オムロンなど)の製品ラインナップと強み
モータ制御、ヒータ制御、省スペース化、特殊環境対応など、用途別のおすすめメーカーと選定ポイント
定格、寿命、安全規格、サポート体制など、選定時に押さえるべき重要ポイント
このガイドを参考に、貴社の設備に最適なコンタクタを見つけ、安定稼働と安全性の向上を実現してください。
2. コンタクタとは?その重要性と種類
産業機械や設備の安定稼働に不可欠な電力制御において、コンタクタは電気回路の「スイッチ」として極めて重要な役割を担っています。単なるON/OFFだけでなく、大容量の電力を安全かつ効率的に制御し、自動化されたシステムの中核を成すことで、生産性の向上と事故防止に貢献しています。
2.1 コンタクタの基本的な役割と仕組み
コンタクタの主な役割は、制御回路からの信号を受けて主回路(電力回路)の開閉を行うことです。これにより、モータの始動・停止、ヒータのON/OFF、照明の点滅など、様々な電気負荷を遠隔で、または自動的に制御することが可能になります。
その基本的な仕組みは、電磁石の原理に基づいています。コンタクタ内部には「コイル」が内蔵されており、このコイルに制御電圧を印加すると電磁石が発生します。この電磁力によって可動鉄心が吸引され、それに連動して主回路の「接点」が開閉する仕組みです。接点が開くことで回路は遮断され、閉じることで電流が流れるようになります。
また、多くのコンタクタには主接点とは別に「補助接点」も備わっています。この補助接点は、自己保持回路の構築や、複数の機器間のインターロック(相互作用防止)など、制御回路の複雑なロジックを実現するために利用されます。コンタクタは、高電圧・大電流を安全に制御するための必須コンポーネントであり、作業者の安全確保や設備の保護、そしてシステムの自動化・効率化に不可欠です。
2.2 主なコンタクタの種類と特徴
コンタクタは、その動作原理や機能によっていくつかの種類に分けられます。ここでは、産業用途で一般的に使用される主要なコンタクタの種類とその特徴について解説します。
2.2.1 電磁接触器(MC)
電磁接触器(Magnetic Contactor、略称MC)は、電磁石の力で主回路の接点を開閉する最も基本的なコンタクタです。コイルへの通電・非通電によって、機械的な接点を通じて電力回路を入り切りします。過負荷保護機能は内蔵しておらず、純粋な開閉動作に特化しています。
特徴:
電磁石の原理に基づく機械的な接点開閉。
主回路のON/OFF制御に特化。
構造が比較的シンプルで、信頼性が高い。
過負荷保護機能は持たないため、別途サーマルリレーなどと組み合わせて使用する必要がある。
主な用途:
モータのON/OFF制御(単独またはサーマルリレーと組み合わせ)。
ヒータや電熱線の開閉。
照明回路の制御。
一般動力負荷の開閉。
2.2.2 電磁開閉器(MS)
電磁開閉器(Magnetic Starter、略称MS)は、電磁接触器に過負荷保護用の熱動形過負荷継電器(サーマルリレー)を組み合わせたものです。主にモータの始動・停止・保護を目的として使用されます。モータに過大な電流が流れた際に、サーマルリレーがそれを検知して電磁接触器を遮断し、モータの焼損を防ぎます。
特徴:
電磁接触器とサーマルリレーが一体化されている。
モータの過負荷保護機能を内蔵しているため、別途保護装置を用意する必要がない。
配線がシンプルになり、省スペース化に貢献する。
主な用途:
ポンプ、ファン、コンベアなどのモータの始動・停止・保護。
産業用機械の動力制御。
電磁接触器と電磁開閉器の主な違いは、以下の表で整理できます。
2.2.3 ソリッドステートコンタクタ(SSC)
ソリッドステートコンタクタ(Solid State Contactor、略称SSC)は、半導体素子(サイリスタ、トライアックなど)を用いて主回路の開閉を行う無接点コンタクタです。機械的な接点を持たないため、従来の電磁式コンタクタとは異なる多くの特徴とメリットを持ちます。
特徴:
機械的な可動部がないため、開閉寿命が非常に長い。
高速での開閉が可能(高頻度開閉に対応)。
動作音がなく、静音性に優れる。
接点摩耗による粉塵が発生しない。
ゼロクロス機能により、ノイズの発生を抑制し、負荷へのストレスを軽減。
電磁式に比べて発熱が大きい場合があり、放熱対策が必要となることがある。
主な用途:
高頻度でON/OFFを繰り返すヒータ制御(温度の精密制御)。
半導体製造装置やクリーンルーム内での使用。
騒音や振動を嫌う環境。
長寿命が求められる設備。
電磁式コンタクタとソリッドステートコンタクタの比較は以下の通りです。
3. 主要コンタクタ メーカー徹底比較
コンタクタの選定において、どのメーカーの製品を選ぶかは、システムの安定稼働やコスト、メンテナンス性に大きく影響します。ここでは、国内市場で高いシェアを誇る主要メーカーと、その他注目すべきメーカーの製品群を徹底的に比較し、それぞれの強みと特徴を解説します。
3.1 国内主要コンタクタ メーカーの紹介
日本国内では、長年にわたり産業界を支えてきた信頼性の高いコンタクタメーカーが複数存在します。それぞれのメーカーが持つ独自の技術と強みを理解することで、最適な製品選びに繋がります。
3.1.1 三菱電機のコンタクタ
三菱電機は、FA(ファクトリーオートメーション)分野において国内トップクラスのシェアを誇る総合電機メーカーであり、そのコンタクタ製品も高い信頼性と実績を兼ね備えています。特にモータ制御用としては、長年の経験と技術が凝縮された製品群を提供しています。
代表的なシリーズとしては、汎用性の高い「MS-Tシリーズ」が挙げられます。このシリーズは、小型化と高性能化を両立しており、様々な産業機械や設備に幅広く採用されています。また、環境負荷低減に配慮した省エネタイプや、高頻度開閉に対応する高耐久タイプなど、多様なニーズに応えるラインナップが特徴です。
3.1.2 富士電機のコンタクタ
富士電機は、電力・社会インフラから産業用機器まで幅広い分野で製品を提供する重電メーカーです。コンタクタにおいても、高い品質と耐久性を追求した製品を供給しており、特に電力系統や大型モータ制御といった、高い信頼性が求められる用途で強みを発揮します。
「SCシリーズ」に代表される富士電機のコンタクタは、過酷な使用環境下でも安定した性能を発揮する堅牢性が評価されています。また、省エネ性能の向上や、配線作業の効率化を考慮した設計など、現場での使いやすさにも配慮がなされています。グローバルな安全規格への対応も充実しており、海外展開する設備にも安心して採用できます。
3.1.3 オムロンのコンタクタ
オムロンは、制御機器やFAシステムにおいて世界的に高い評価を得ているメーカーです。コンタクタ製品においても、その制御技術と連携性の高さが特徴です。特に、PLC(プログラマブルロジックコントローラ)などの制御機器と組み合わせることで、システム全体の効率化と信頼性向上に貢献します。
オムロンのコンタクタは、盤内省スペース化に貢献する小型・薄型設計の製品が多く、装置の小型化や設計自由度の向上に寄与します。また、配線作業の容易さや、メンテナンス性を考慮した設計も特徴の一つです。FAシステム全体でのソリューション提案を得意としており、コンタクタ単体だけでなく、システム全体の最適化を求める場合に強みを発揮します。
3.1.4 その他の注目コンタクタ メーカー
上記3社以外にも、日本国内および海外には優れたコンタクタメーカーが存在し、特定の用途やコストパフォーマンスにおいて魅力的な選択肢となります。
河村電器産業: 配電盤・分電盤の総合メーカーとして、盤内機器との連携を考慮したコンタクタを提供しています。特に、住宅用や小規模設備向けの製品で実績があります。
パナソニック: 一部の産業用機器や住宅設備向けに、信頼性の高いコンタクタを提供しています。
シュナイダーエレクトリック(Schneider Electric): フランスに本社を置くグローバル企業で、日本市場でも広く流通しています。産業用制御機器の総合メーカーとして、広範なラインナップと高いグローバルスタンダードを特徴とします。特に、IEC規格に準拠した製品が多く、国際的なプロジェクトで採用されるケースも少なくありません。
シーメンス(Siemens): ドイツの電機メーカーで、FA分野において三菱電機と並ぶ世界的リーダーです。日本市場でもそのコンタクタは高い評価を得ており、高性能かつ堅牢な製品が特徴です。特に、大規模な産業プラントやインフラ設備での採用実績が豊富です。
ABB: スイスに本社を置くグローバル企業で、電力・オートメーション技術の分野で世界をリードしています。日本市場においても、信頼性の高いコンタクタを提供しており、特に高電圧・高電流用途や特殊な環境下での使用に適した製品も扱っています。
3.2 各コンタクタ メーカーの強みと得意分野
各メーカーのコンタクタは、それぞれ異なる強みと得意分野を持っています。以下の表で、主要メーカーの特性を比較し、選定の参考にしてください。
この比較表はあくまで一般的な傾向を示すものであり、具体的な選定においては、個々の製品仕様や必要な機能、コスト、納期、そしてアフターサービスなども総合的に考慮することが重要です。
4. 用途別おすすめコンタクタ メーカーと選定ポイント
コンタクタの選定は、単にメーカーを選ぶだけでなく、どのような用途で、どのような環境下で使用するかによって最適な選択肢が大きく変わります。ここでは、主要な用途に焦点を当て、それぞれに適したコンタクタ メーカーとその選定ポイントを詳しく解説します。
4.1 モータ制御におすすめのコンタクタ メーカーと選定ポイント
モータ制御用コンタクタは、起動・停止時の突入電流への耐性や、誘導性負荷の開閉に伴うアーク発生への対応が重要です。また、頻繁な運転・停止が想定されるため、高い開閉寿命も求められます。
選定ポイント:
定格電流・定格電圧: 制御対象のモータの定格に適合すること。
開閉容量: モータの起動電流(突入電流)に耐えうる遮断容量を持つこと。
機械的・電気的寿命: 運転頻度を考慮し、十分な寿命を持つ製品を選ぶこと。
保護機能: 過負荷保護用のサーマルリレーとの組み合わせや、一体型製品の有無。
サイズと設置性: 制御盤内のスペースに収まるか、配線作業のしやすさ。
おすすめコンタクタ メーカー:
4.2 ヒータ制御におすすめのコンタクタ メーカーと選定ポイント
ヒータ制御では、主に抵抗負荷の開閉が中心となります。モータのような大きな突入電流は少ないですが、定常的な電流が大きいため、発熱への対策や安定した通電性能が重要です。特に、高頻度な温度制御が必要な場合は、ソリッドステートコンタクタ(SSC)も選択肢に入ります。
選定ポイント:
定格電流・定格電圧: 制御対象のヒータの定格に適合すること。
周囲温度と放熱: 高温環境下での使用や、自身の発熱に対する放熱対策が十分か。
開閉頻度: 頻繁なON/OFF制御が必要な場合、機械的寿命が長い製品やSSCの検討。
ノイズ対策: SSCを使用する場合、ノイズ発生を抑えるゼロクロス機能の有無。
おすすめコンタクタ メーカー:
4.3 盤内省スペース化に貢献するコンタクタ メーカー
近年、制御盤の小型化・高密度化が進む中で、コンタクタにも省スペース性が強く求められています。幅の狭いスリムタイプや、配線工数を削減できる製品が注目されています。
選定ポイント:
製品幅: DINレール取り付け時の占有幅。
奥行き・高さ: 盤の深さやレイアウトに影響。
配線方式: 前面配線など、配線作業が容易で工数を削減できるか。
補助接点ブロック: 省スペースで追加できるか。
おすすめコンタクタ メーカー:
4.4 特殊環境下での使用に適したコンタクタ メーカー
粉塵が多い環境、高温多湿、低温、振動・衝撃が激しい場所、腐食性ガスが発生する場所など、特殊な環境下で使用されるコンタクタには、高い耐環境性能が求められます。防塵・防滴構造や耐熱・耐寒性能、耐振動性能などが選定の鍵となります。
選定ポイント:
保護構造(IP等級): 粉塵や水の侵入に対する保護レベル。
使用温度範囲: 極端な高温・低温環境に対応できるか。
耐振動・耐衝撃性能: 鉄道車両や移動機械などでの使用に適応できるか。
耐腐食性: 化学工場など腐食性ガスが発生する環境への対応。
防爆認証: 可燃性ガスや粉塵が存在する危険場所での使用可否。
おすすめコンタクタ メーカー:
特定のメーカーが全ての特殊環境に特化しているわけではなく、各メーカーが特定の耐環境性能を強化した製品を提供しています。選定時には、要求される環境条件を明確にし、各メーカーの製品カタログや技術資料で適合するモデルを確認することが不可欠です。
特殊環境下での使用は、安全に関わる重要な要素であるため、必ずメーカーの技術担当者や専門業者と相談し、適切な製品を選定するようにしてください。
4.5 コストパフォーマンスを重視する際のコンタクタ メーカー選び
コンタクタのコストパフォーマンスは、単に初期導入費用だけでなく、長期的な運用における総コスト(TCO:Total Cost of Ownership)で評価することが重要です。耐久性、消費電力、メンテナンス性、交換部品の入手性、技術サポートなどが含まれます。
選定ポイント:
初期導入コスト: 製品本体の価格。
耐久性と寿命: 交換頻度が低ければ、長期的なコストは抑えられる。
消費電力: 運転中の消費電力が少ないほどランニングコストが低い。
メンテナンス性: 点検・交換が容易か、専用工具が不要か。
交換部品の入手性: 万が一の故障時に迅速に部品が手に入るか。
技術サポート: 導入後のトラブル対応や技術的な相談体制。
おすすめコンタクタ メーカー:
日本国内の主要コンタクタ メーカーは、総じて高い品質と信頼性を提供しており、結果として長期的な視点でのコストパフォーマンスに優れています。安価な海外製品も存在しますが、品質やサポート体制を十分に確認する必要があります。
コストパフォーマンスを追求する際は、目先の価格だけでなく、製品のライフサイクル全体を見据えた評価を行うことが、最終的な満足度を高める鍵となります。
5. コンタクタ選定で押さえるべき重要ポイント
コンタクタを選定する際には、単に電流容量だけでなく、その設置環境、使用頻度、将来的なメンテナンス性まで多角的に考慮することが重要です。ここでは、失敗しないコンタクタ選びのために特に押さえておくべきポイントを詳しく解説します。
5.1 定格と容量の確認
コンタクタの選定において最も基本的ながら、最も重要なのが「定格」と「容量」の適切な確認です。これは、コンタクタが安全かつ安定して動作するために不可欠な要素となります。
5.1.1 定格電流と定格電圧
コンタクタには、主回路の「定格電流」と「定格電圧」、そして操作コイルの「定格電圧」が存在します。
主回路の定格電流: 制御対象の負荷(モータ、ヒータなど)が流す最大電流を考慮し、それに余裕を持たせた定格電流のコンタクタを選定します。特にモータなどの誘導性負荷では、始動時に定格電流の数倍の突入電流が流れるため、そのピーク電流にも耐えられる容量が必要です。
主回路の定格電圧: 制御対象の電源電圧と一致している必要があります。
操作コイルの定格電圧: コンタクタを動作させるための制御電源電圧と一致している必要があります。AC100V、AC200V、DC24Vなど、使用する制御電源に合わせて選択します。
5.1.2 負荷の種類に応じた選定
コンタクタの定格は、接続される負荷の種類によって大きく変わります。国際規格であるIEC(国際電気標準会議)では、負荷の種類に応じた使用カテゴリー(AC-1、AC-3など)が定められており、これに基づいて選定することが一般的です。
AC-1(抵抗負荷): ヒータや照明など、純粋な抵抗性負荷に適しています。定格電流に近い選定が可能です。
AC-3(かご形モータ負荷): 一般的な三相かご形モータの始動・停止に適しています。始動時の突入電流に耐える能力が求められます。
AC-4(インチング・プラッギング): 頻繁な始動・停止や逆転運転を行うモータ負荷に適しており、AC-3よりも高い開閉能力と耐久性が求められます。
負荷の種類と実際の運転条件を正確に把握し、適切な使用カテゴリーのコンタクタを選定することが、故障や短寿命を防ぐ上で極めて重要です。
5.2 開閉寿命と耐久性
コンタクタの寿命は、その信頼性とメンテナンスコストに直結する重要な要素です。コンタクタの寿命には、主に「電気的寿命」と「機械的寿命」の二種類があります。
電気的寿命: 接点に電流が流れた状態で開閉を繰り返すことにより、アーク放電によって接点が消耗・劣化していく寿命です。開閉頻度や負荷電流の大きさ、負荷の種類(誘導性負荷か抵抗性負荷か)によって大きく変動します。頻繁な開閉が予想される用途では、電気的寿命が長い製品、またはアーク消弧能力に優れた製品を選ぶ必要があります。
機械的寿命: 接点に電流が流れていない状態で、コイルの励磁・消磁による機械的な動作を繰り返すことによる寿命です。接点の消耗は伴いませんが、機構部の摩耗や疲労によって動作不良を起こす可能性があります。
特に、モータの頻繁なON/OFF制御や、高速な位置決めを伴う機械など、開閉頻度が高い用途では、高頻度開閉に対応した耐久性の高いコンタクタを選定することが不可欠です。カタログにはそれぞれの寿命回数が記載されていますので、設計寿命と照らし合わせて確認しましょう。
5.3 安全規格と認証
コンタクタは、産業機械や設備の中核をなす部品であり、その安全性は非常に重要です。そのため、各国や地域で定められた様々な安全規格に適合している必要があります。使用する国や地域、または納入先の要求に応じて、必要な安全規格に適合し、認証を取得している製品を選ぶことが必須です。
主要な安全規格と認証には以下のようなものがあります。
特に海外へ輸出する機械や設備に組み込む場合は、輸出先の国の法規制や顧客の要求を事前に確認し、必要な認証を取得しているコンタクタを選定することがトラブルを避ける上で極めて重要です。
5.4 メンテナンス性と交換部品の入手性
設備が稼働を開始した後も、コンタクタの安定稼働を維持するためには、適切なメンテナンスと、万一の故障時の迅速な対応が求められます。この点で、メンテナンスのしやすさと交換部品の入手性は、長期的な運用コストに大きく影響します。
交換部品の入手性: コイル、補助接点、主接点(大容量品の場合)などは消耗品であり、交換が必要になる場合があります。これらの交換部品が容易に入手できるか、価格は妥当かを確認しましょう。生産中止(ディスコン)のリスクが低い、長期供給が見込めるメーカーの製品を選ぶことが望ましいです。
交換作業の容易さ: 現場での交換作業が簡単に行える設計であるかどうかも重要です。例えば、工具不要でコイルや補助接点を交換できるタイプや、配線が容易な端子構造を持つ製品は、メンテナンス工数を削減できます。
トラブルシューティングのしやすさ: 動作状態が視覚的に確認できるインジケータ付きの製品や、配線図が明確な製品は、トラブル発生時の原因特定と復旧を早めるのに役立ちます。
予期せぬダウンタイムを最小限に抑えるためにも、メンテナンスが容易で、必要な部品が迅速に手に入るメーカーの製品を選ぶことが、結果的に運用コストの削減に繋がります。
5.5 技術サポートとアフターサービス
コンタクタの選定から導入、そして運用に至るまで、メーカーや販売店からの技術サポートとアフターサービスは非常に重要な要素となります。特に、特殊な用途や複雑なシステムに組み込む場合、適切な技術的アドバイスが得られるかどうかが、プロジェクトの成否を分けることもあります。
技術相談体制: 製品選定時や、設計段階での疑問点、トラブル発生時の技術的な問い合わせに対して、迅速かつ的確な回答が得られるサポート体制が整っているかを確認しましょう。専門知識を持った担当者がいるか、オンラインでの情報提供が充実しているかなども判断材料になります。
保証期間と修理サービス: 製品の保証期間や、故障時の修理対応、代替品の提供などのサービス内容を確認します。特に、重要な設備に使用する場合は、緊急時の対応能力が非常に重要になります。
製品トレーニング・資料提供: 製品の正しい使い方やメンテナンス方法に関するトレーニングプログラムが提供されているか、あるいは詳細な取扱説明書や技術資料が充実しているかも、長期的な運用を考慮する上で役立ちます。
単に製品の性能だけでなく、メーカーや販売店が提供するトータルなサポート体制も評価項目に加えることで、導入後の安心感が大きく変わります。特に、初めて使用するメーカーの製品や、新しい技術を搭載したコンタクタを選ぶ際には、手厚いサポート体制が強みとなります。
6. コンタクタ選びに関するよくある質問
6.1 Q1 コンタクタの寿命はどのくらいですか?
コンタクタの寿命は、その種類や使用環境、負荷の種類、開閉頻度によって大きく変動します。一般的に、寿命は「電気的寿命」と「機械的寿命」の2つの側面から評価されます。
電気的寿命:接点の消耗や溶着によって開閉機能が損なわれるまでの寿命です。開閉時のアーク放電による接点の摩耗が主な原因で、特にモータなどの誘導性負荷や高頻度な開閉を伴う用途では短くなる傾向があります。メーカーは定格負荷における開閉回数を公表していますが、これはあくまで目安であり、実際の使用条件によって大きく左右されます。
機械的寿命:可動部の摩耗や疲労によって機械的な動作が維持できなくなるまでの寿命です。コイルの断線やスプリングの劣化などが原因となります。電気的寿命に比べて一般的に長く設定されていますが、振動や衝撃が多い環境では短くなる可能性があります。
多くのコンタクタは、定格条件下で電気的寿命が数十万回から数百万回、機械的寿命が数百万回から数千万回とされています。しかし、周囲温度が高い環境での使用、過負荷での運転、頻繁なON/OFF切り替えなどは、寿命を著しく縮める要因となります。コンタクタの性能を最大限に引き出し、安定稼働を維持するためには、定期的な点検と適切な交換時期の見極めが重要です。
6.2 Q2 海外メーカーのコンタクタを選ぶメリットとデメリットは?
海外メーカーのコンタクタは、その多様な製品ラインナップと特定の強みから選択肢の一つとなりますが、国内メーカー品と比較して考慮すべき点があります。以下に主なメリットとデメリットをまとめました。
海外メーカー品を選ぶ際は、初期コストだけでなく、長期的な運用におけるサポート体制、部品供給、そして国内の法規適合性まで総合的に評価することが重要です。
6.3 Q3 古いコンタクタの交換時に注意すべき点は?
古いコンタクタを交換する際には、単に同じ型番の製品を探すだけでなく、いくつかの重要な点に注意を払う必要があります。特に生産終了品の場合は、代替品の選定がより複雑になります。
6.3.1 互換性の確認
新しいコンタクタを選定する際、最も重要なのは既存の設備との互換性です。以下の項目を詳細に確認しましょう。
定格(電圧・電流):制御回路のコイル電圧、主回路の定格電流、開閉容量が既存品と同等以上であることを確認します。
寸法と取付方法:盤内のスペースに収まるか、DINレール取付やネジ止めなどの取付方法が同じかを確認します。
端子配置:主回路端子、コイル端子、補助接点端子の配置が既存品と同じであれば、配線変更の手間を最小限に抑えられます。
補助接点構成:必要な補助接点(常開/常閉)の数と種類が確保できるかを確認します。
6.3.2 生産終了品の代替品選定
古いコンタクタがすでに生産終了している場合、メーカーが提供する後継機種や互換性のある代替品を探すことになります。後継機種は機能が向上していることが多いですが、寸法や端子配置が異なる場合があるため、必ず仕様書で確認が必要です。場合によっては、他メーカーの同等品を検討する必要も出てきます。
6.3.3 配線と制御回路の確認
コンタクタの交換に伴い、配線の引き直しが必要になる場合があります。特に端子台の形状や配置が異なる場合、既存の配線長では届かない、あるいは無理な力がかかる可能性があります。また、新しいコンタクタのコイル消費電力が異なる場合、制御回路の電源容量や保護機器(ブレーカーなど)の見直しが必要になることもあります。
6.3.4 安全対策の徹底
コンタクタの交換作業は、必ず設備の電源を遮断し、残留電荷がないことを確認した上で行ってください。誤操作による感電や短絡事故を防ぐため、ロックアウト・タグアウト(LOTO)などの安全手順を徹底することが不可欠です。作業前には必ず回路図を確認し、関連する全ての電源が遮断されていることを確認しましょう。
6.3.5 専門家への相談
交換作業に不安がある場合や、複雑な制御回路が関わる場合は、電気工事士や制御盤メーカー、コンタクタメーカーの技術サポートなど、専門家への相談を強く推奨します。適切なアドバイスやサポートを受けることで、トラブルを未然に防ぎ、安全かつ確実に交換作業を行うことができます。
7. まとめ
本記事では、コンタクタ選びで失敗しないためのポイントと主要メーカーの比較を詳しく解説しました。コンタクタは、モータやヒータ制御など、産業機械の安全性と効率を支える重要な部品です。三菱電機、富士電機、オムロンといった国内主要メーカーは、それぞれ得意な分野や製品ラインナップを持ちます。選定においては、用途に応じた定格容量、開閉寿命、安全規格、そして導入後のサポート体制を総合的に評価することが不可欠です。これらの情報を踏まえ、貴社の設備に最適なコンタクタを選び、安定稼働とコスト削減を実現してください。
企業情報
DCシリーズ
ED・SD・SU・Busbarシリーズ
企業情報
オルブライト・ジャパン
株式会社
- 〒353-0004
埼玉県志木市本町6-26-6-101 - TEL.048-485-9592
- FAX.048-485-9598
ED・SD・SU・Busbarシリーズ
- DCコンタクタの輸入販売
- 非常用電源遮断スイッチの輸入販売
パワーリレー・スイッチ・直流電磁接触器 コンタクタ・汎用リレー・車載リレー 高電圧リレーなどに関する製品のお問い合わせ、お気軽にご連絡ください。